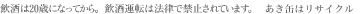
銀塩カメラの本 その1
銀塩カメラが少し集まってくると、
銀塩カメラの本も少し欲しくなってきます。
自分の持っているカメラがどんなカメラであったのか、
知りたくなりますよね。
そこで、色々な本が出ていますが、
今日は三冊をご紹介します。
先ずは、この本です。
佐々木果編著「コンタックスはいかにキエフとなったか」

冊子のスタイルからして、
学術雑誌の様な感じがします。
これを少し読んでみると、
似たようなカメラに実に多くのバリエーションがあることが分かります。
Kievのコレクターは、実に奥が深いのだろうな、
と思わずにはいられません。
次は、クリバヤシ-ペトリカメラの本です。
ライカやコンタックスの本はたくさん出ていますが、
ペトリにも出ていたのですね、という感じです。

ペトリのカメラはユニークなスタイルをしたものが多かったのですが、
日本でもペトリの単行本は出ていたのでしょうか。
この本の著者J. R. Bairdはどうやって調べたのでしょうか。
そういえば、この本も少し考えています(単に写真の腕が悪いだけですが)。
さらに、購入店のプライスシールまであります(シカゴのWabashi St. のCentralCameraです)。
最後は、銀塩カメラのメンテの本。
これです。

カラーの本で、分解や組み立てがよくわかります。
写真集としても綺麗な本かもしれません。
ただ、口の悪いあるカメラ修理屋さんは、
世に出ている修理の本は、
分解の仕方と組み立て方があるだけで、
直しかたは書いてない、
とさえ言っていました。
極端な言い方ですが、彼なりに修理に自信があるのかも知れません。
では、良い週末を。
>>トップへ
銀塩カメラの本も少し欲しくなってきます。
自分の持っているカメラがどんなカメラであったのか、
知りたくなりますよね。
そこで、色々な本が出ていますが、
今日は三冊をご紹介します。
先ずは、この本です。
佐々木果編著「コンタックスはいかにキエフとなったか」

冊子のスタイルからして、
学術雑誌の様な感じがします。
これを少し読んでみると、
似たようなカメラに実に多くのバリエーションがあることが分かります。
Kievのコレクターは、実に奥が深いのだろうな、
と思わずにはいられません。
次は、クリバヤシ-ペトリカメラの本です。
ライカやコンタックスの本はたくさん出ていますが、
ペトリにも出ていたのですね、という感じです。

ペトリのカメラはユニークなスタイルをしたものが多かったのですが、
日本でもペトリの単行本は出ていたのでしょうか。
この本の著者J. R. Bairdはどうやって調べたのでしょうか。
そういえば、この本も少し考えています(単に写真の腕が悪いだけですが)。
さらに、購入店のプライスシールまであります(シカゴのWabashi St. のCentralCameraです)。
最後は、銀塩カメラのメンテの本。
これです。

カラーの本で、分解や組み立てがよくわかります。
写真集としても綺麗な本かもしれません。
ただ、口の悪いあるカメラ修理屋さんは、
世に出ている修理の本は、
分解の仕方と組み立て方があるだけで、
直しかたは書いてない、
とさえ言っていました。
極端な言い方ですが、彼なりに修理に自信があるのかも知れません。
では、良い週末を。
>>トップへ
Agfa Automatic 66
銀塩カメラファンの中には、
フィルムメーカーのカメラやレンズ、
特にレンズを好きな方が結構おられるようです。
つまり、
Fuji
Konica
Kodak
Agfa
のカメラやレンズですね。
そこで、今日のカメラはこれです。

Agfaの中判蛇腹カメラ、Agfa Automatic 66です。
現状品を、Kodak Retina Ⅲc(小窓)と同じ程度の価格で購入しました。
ただ、
問題は、このカメラの場合、殆どがこのトラブルといわれる自動制御、
これの修理費用が嵩むということです。
それに、このカメラを直せるところは日本ではここしかありません。
浅草にある有名な、このお店です。
空気自動制御とかいう特殊なメカニズムのため、
修理代金は美品のRicoh GR lens 21mmF3.5と同じ程度の価格が見積もられました。
こうなると、少し嬉しくなってくるから不思議です。
銀塩カメラを集めようとすると、
機械式時計やラジオなどでもそうでしょうが、
メンテナンス費用が定期的に発生します。
ボクのような少ないコレクションでも、
統計的にみると購入費の凡そ5%が修理代金になっています。
カメラの修理はやはり腕がものを言いますから、
専門家に任せる以外にありません。
この数字、あなたはどう思われますか。
一般に、修理費が高くつくカメラがあります。
例えば、こんなカメラです。

同じくフィルムメーカーKodakのEktra 35です。
そういえば、ロシアカメラのキエフの一眼レフのカメラも高くついたことを思い出しました。
でも、身の回りのカメラは良い状態にしておきたいですね。
>>トップへ
フィルムメーカーのカメラやレンズ、
特にレンズを好きな方が結構おられるようです。
つまり、
Fuji
Konica
Kodak
Agfa
のカメラやレンズですね。
そこで、今日のカメラはこれです。

Agfaの中判蛇腹カメラ、Agfa Automatic 66です。
現状品を、Kodak Retina Ⅲc(小窓)と同じ程度の価格で購入しました。
ただ、
問題は、このカメラの場合、殆どがこのトラブルといわれる自動制御、
これの修理費用が嵩むということです。
それに、このカメラを直せるところは日本ではここしかありません。
浅草にある有名な、このお店です。
空気自動制御とかいう特殊なメカニズムのため、
修理代金は美品のRicoh GR lens 21mmF3.5と同じ程度の価格が見積もられました。
こうなると、少し嬉しくなってくるから不思議です。
銀塩カメラを集めようとすると、
機械式時計やラジオなどでもそうでしょうが、
メンテナンス費用が定期的に発生します。
ボクのような少ないコレクションでも、
統計的にみると購入費の凡そ5%が修理代金になっています。
カメラの修理はやはり腕がものを言いますから、
専門家に任せる以外にありません。
この数字、あなたはどう思われますか。
一般に、修理費が高くつくカメラがあります。
例えば、こんなカメラです。

同じくフィルムメーカーKodakのEktra 35です。
そういえば、ロシアカメラのキエフの一眼レフのカメラも高くついたことを思い出しました。
でも、身の回りのカメラは良い状態にしておきたいですね。
>>トップへ
骨董市で買ったもの
この辺りで、定期的に行われる骨董市で比較的大きなものは、
大須観音の骨董市です。
サイトはここです。
18日に行ってきたのですが、
こんな感じです。

Canon PowerShot G9で撮影しました(下の画像イメージも同じです)。
この骨董市には、
銀塩カメラを出されているお店が数件あり、
やはり男性が主な客で、
今でも結構人気がありました。
ただ、出品されているものは、
Canon Demi
Minolta HI-MATIC
Yashica Electro 35
Konica C35
----
などのレンズ固定式レンジファインダー機、
しかも、
電気カメラでした。
そんな中、ボクが買ったのは-----
コレです。

Konihoodです。
取付径の大きさから、
Hexanon48mmF2あたりのレンズがついたレンジファインダーカメラ用だと思います。
お値段は500円でした。
市でつきものの交渉はせず、値切らずに購入しました。
太っ腹ですね。
こういう買い方をすると、自分が大きくなったような感じがします。
骨董市に出ているものは、
業者市で盆中幾ら(一山幾ら)で出されたものが多いので、
掘り出しモノは滅多にないといわれています。
でも、銀塩カメラのアクセサリは狙い目です。
汚れていても、不具合はありませんから。
みなさんは、どのように骨董市を楽しまれていますか。
>>トップへ
大須観音の骨董市です。
サイトはここです。
18日に行ってきたのですが、
こんな感じです。

Canon PowerShot G9で撮影しました(下の画像イメージも同じです)。
この骨董市には、
銀塩カメラを出されているお店が数件あり、
やはり男性が主な客で、
今でも結構人気がありました。
ただ、出品されているものは、
Canon Demi
Minolta HI-MATIC
Yashica Electro 35
Konica C35
----
などのレンズ固定式レンジファインダー機、
しかも、
電気カメラでした。
そんな中、ボクが買ったのは-----
コレです。

Konihoodです。
取付径の大きさから、
Hexanon48mmF2あたりのレンズがついたレンジファインダーカメラ用だと思います。
お値段は500円でした。
市でつきものの交渉はせず、値切らずに購入しました。
太っ腹ですね。
こういう買い方をすると、自分が大きくなったような感じがします。
骨董市に出ているものは、
業者市で盆中幾ら(一山幾ら)で出されたものが多いので、
掘り出しモノは滅多にないといわれています。
でも、銀塩カメラのアクセサリは狙い目です。
汚れていても、不具合はありませんから。
みなさんは、どのように骨董市を楽しまれていますか。
>>トップへ
Nikon 35Ti
Nikonのカメラのことを書きます。
Nikonのカメラのことがこのブログ書けるようになったのは、
大変な進歩の様に感じられます。
昔からNikonのカメラは上手い人が使うイメージが強かったので。
それで、ボクらしく、先ずはコンパクトカメラからです。
Nikon 35Ti
から始めます。
このカメラについてはたくさんのサイトやブログがあって、
例えばこのようなサイトですが、
このため特に書き入れることはないのですが、
やはり何と言っても上部のアナログ針が特徴でした。
当時は面白い仕掛けだなと思っていました。
作例というほどのものではありませんが、
猫です。

南仏の観光スポットでの撮影です。
ところで、
中古カメラのサイトでアクセスが多いのは、
このサイト
と某紙が報じていました。
1日10万PVのアクセスがあるそうです。
このブログとは比べ物になりません。
このサイトには、
専門雑誌による価格比較サイト的な面もありますが、
検索機能が便利ですね。
ただ、インターネットによって、
もともとある程度の相場が形成されていた市場が、
ますます、固定化されてしまった様にさえ思えます。
このサイトの取扱商品を見ていると、
つまり参加されている販売店さんの商品に他ならないのですが、
概ね売れ筋は有りますが、
Minolta MC/MD 40-80mmF2.8
という形が四角い印象のズームレンズや
EBC Fujinon 35mmF1.9(M42)
などといった、
極めてレアモノや主流のモノではないけれど、
以前は比較的良く目にしたけれど、
ボクにとっては少し気になるアイテムがなかなか見つかりません。
中古市場はやはり、
ある意味、
あるものはあるけど、
無いものはない、
ということでしょうか。
>>トップへ
Nikonのカメラのことがこのブログ書けるようになったのは、
大変な進歩の様に感じられます。
昔からNikonのカメラは上手い人が使うイメージが強かったので。
それで、ボクらしく、先ずはコンパクトカメラからです。
Nikon 35Ti
から始めます。
このカメラについてはたくさんのサイトやブログがあって、
例えばこのようなサイトですが、
このため特に書き入れることはないのですが、
やはり何と言っても上部のアナログ針が特徴でした。
当時は面白い仕掛けだなと思っていました。
作例というほどのものではありませんが、
猫です。

南仏の観光スポットでの撮影です。
ところで、
中古カメラのサイトでアクセスが多いのは、
このサイト
と某紙が報じていました。
1日10万PVのアクセスがあるそうです。
このブログとは比べ物になりません。
このサイトには、
専門雑誌による価格比較サイト的な面もありますが、
検索機能が便利ですね。
ただ、インターネットによって、
もともとある程度の相場が形成されていた市場が、
ますます、固定化されてしまった様にさえ思えます。
このサイトの取扱商品を見ていると、
つまり参加されている販売店さんの商品に他ならないのですが、
概ね売れ筋は有りますが、
Minolta MC/MD 40-80mmF2.8
という形が四角い印象のズームレンズや
EBC Fujinon 35mmF1.9(M42)
などといった、
極めてレアモノや主流のモノではないけれど、
以前は比較的良く目にしたけれど、
ボクにとっては少し気になるアイテムがなかなか見つかりません。
中古市場はやはり、
ある意味、
あるものはあるけど、
無いものはない、
ということでしょうか。
>>トップへ
英語を学ぶコツ
サイドバーに突然、オンライン英会話のバナーが加わりました。
これは、今流行りの無料通信ソフト、Skypeを利用したもので、
主にフィリピンの先生と日本人の生徒さんを繋げるサイトが多いようです。
なぜ、バナーを設置したかと言うと、
友人がやり始めて、それで会員さんが欲しいというのです。
別にアフィリ収入など入りませんが、
面白い企画で、リーズナブルな料金なのでご紹介しておきます。
無料体験レッスンを2回受けられます。
如何ですか?
オンライン英会話のEnglishTalk
ボクは英語が上手いわけでもありませんが(日本語も少し拙いか)、
でも、上手くなる方法に好きな分野を英語で学ぶ、
という方法はあるかなあ、と思います。
クラシックカメラの世界を英語で学ぶ、
eBayの出品のために英語を学ぶ、
などなど。
今日の写真です。

サンマルコ寺院だったでしょうか。
ミラノから電車で2時間半かけて行ったように覚えています。
当時2000円くらいで買ったFuji Cardia Travel Mini DP、28mm側で撮影。
もう少し、構図が何とかならなかったものかなあ、と思います。
印象は、人も鳩も多かった、というものでした。
安い銀塩カメラでしたが、まあまあ好きでした。
そして、無くしても惜しくない、というのが大きな魅力でした。
またぼちぼちブログを更新していきます。
>>トップへ
これは、今流行りの無料通信ソフト、Skypeを利用したもので、
主にフィリピンの先生と日本人の生徒さんを繋げるサイトが多いようです。
なぜ、バナーを設置したかと言うと、
友人がやり始めて、それで会員さんが欲しいというのです。
別にアフィリ収入など入りませんが、
面白い企画で、リーズナブルな料金なのでご紹介しておきます。
無料体験レッスンを2回受けられます。
如何ですか?
オンライン英会話のEnglishTalk
ボクは英語が上手いわけでもありませんが(日本語も少し拙いか)、
でも、上手くなる方法に好きな分野を英語で学ぶ、
という方法はあるかなあ、と思います。
クラシックカメラの世界を英語で学ぶ、
eBayの出品のために英語を学ぶ、
などなど。
今日の写真です。

サンマルコ寺院だったでしょうか。
ミラノから電車で2時間半かけて行ったように覚えています。
当時2000円くらいで買ったFuji Cardia Travel Mini DP、28mm側で撮影。
もう少し、構図が何とかならなかったものかなあ、と思います。
印象は、人も鳩も多かった、というものでした。
安い銀塩カメラでしたが、まあまあ好きでした。
そして、無くしても惜しくない、というのが大きな魅力でした。
またぼちぼちブログを更新していきます。
>>トップへ
タイトルを変える
今年になって初めてのブログです。
なんだか季刊の様になってしまったので、
もう少し頑張ろうと思っています。
イチオシの銀塩カメラでは、
結局何が言いたいのか、
よくわからないのではないかな、
と自分なりに考え、
タイトルを変更しました。
でも、書いていることやスタイルは変えようがありません。
で、写真です。

家の近くですが、
LeicaのSummaron35mmF3.5で撮りました-----
というのは嘘で、
先回ご紹介したRicohのスケルトンモデルのコンパクトカメラでの撮影です。
この日は寒かった。
最近は中古カメラの市場が低迷です。
経済が悪いのと、
円高で輸入に有利なのと、
こんな様な背景でしょうか。
特に、コンパクトカメラは、
例えば人気のあるRicohGR21にしても、
かなり安くなってきています。
また普通に撮るのであれば、
最近のコンパクトデジカメ、
例えばキヤノンのG10とかで十分な気がします。
ですが、
銀塩カメラならではのよさもあり、
引き続き、その魅力についてブログを書いて行こうと思っています。
今年も宜しくお願いします。
>>トップへ
なんだか季刊の様になってしまったので、
もう少し頑張ろうと思っています。
イチオシの銀塩カメラでは、
結局何が言いたいのか、
よくわからないのではないかな、
と自分なりに考え、
タイトルを変更しました。
でも、書いていることやスタイルは変えようがありません。
で、写真です。

家の近くですが、
LeicaのSummaron35mmF3.5で撮りました-----
というのは嘘で、
先回ご紹介したRicohのスケルトンモデルのコンパクトカメラでの撮影です。
この日は寒かった。
最近は中古カメラの市場が低迷です。
経済が悪いのと、
円高で輸入に有利なのと、
こんな様な背景でしょうか。
特に、コンパクトカメラは、
例えば人気のあるRicohGR21にしても、
かなり安くなってきています。
また普通に撮るのであれば、
最近のコンパクトデジカメ、
例えばキヤノンのG10とかで十分な気がします。
ですが、
銀塩カメラならではのよさもあり、
引き続き、その魅力についてブログを書いて行こうと思っています。
今年も宜しくお願いします。
>>トップへ
Ricoh FF-9SD Limited
銀塩カメラ関係の書籍では、
枻出版社の書籍が目立ちます。
最近は、蜂谷秀人さんの「ずんちゃちゃカメラ節」など三冊が刊行されました。
アフィリエイトリンクをサイドバーに入れていきましたので、ご覧下さい。*
池田葉子さんの「マイ・フォト・ディズ」には、
トイカメラやポラロイドで撮影された作品が多く載っています。
* 今現在は消しています。
さて、トイカメラといえば、ボクにはこのカメラが何となくその範疇に入るような気がしています。

Ricoh FF-9SD Limitedです。
コンパクトカメラのスケルトン仕様で、他にも何台か、こうしたカメラがあるようです。
飛騨高山では、雪解けを待って伐採が始まります。
凡そ90年生のヒノキの切り株の上において撮影しました。
枻出版社の書籍が目立ちます。
最近は、蜂谷秀人さんの「ずんちゃちゃカメラ節」など三冊が刊行されました。
アフィリエイトリンクをサイドバーに入れていきましたので、ご覧下さい。*
池田葉子さんの「マイ・フォト・ディズ」には、
トイカメラやポラロイドで撮影された作品が多く載っています。
* 今現在は消しています。
さて、トイカメラといえば、ボクにはこのカメラが何となくその範疇に入るような気がしています。
Ricoh FF-9SD Limitedです。
コンパクトカメラのスケルトン仕様で、他にも何台か、こうしたカメラがあるようです。
飛騨高山では、雪解けを待って伐採が始まります。
凡そ90年生のヒノキの切り株の上において撮影しました。
XR Rikenon 55mmF1.2
銀塩カメラの中古の売れ行きはあまりパッとせず、
一方、トイカメラがよく売れているそうです。
数千円から一万円台前半で買えて人気があるそうです。
先日も、あるHP作成業者の方が、
とても興味があって欲しいと話されていました。
いつか書いてみます。
銀塩カメラでも、
トップスペックのアイテムは今でも人気で、
結構、いいお値段です。
例えば、Contax Planar 55mmF1.2なんて言うのは、
状態がよければ恐ろしく高いレンズです。
大抵は殆ど使用していないのではないかと思えるので、
殆どの中古商品が高いことになります。
これに比べて、Ricoh XR Rikenon 55mmF1.2は
随分と安いレンズです。
確か、中古なら1万円台後半で売っていたのではないでしょうか。

Ricoh XR Solar + XR Rikenon 55mmF1.2
冬のパリです。
なぜか、海外に行くときは安いセットになります。
でも、海外の方が人を意識せずにシャッターを切れます。
一方、トイカメラがよく売れているそうです。
数千円から一万円台前半で買えて人気があるそうです。
先日も、あるHP作成業者の方が、
とても興味があって欲しいと話されていました。
いつか書いてみます。
銀塩カメラでも、
トップスペックのアイテムは今でも人気で、
結構、いいお値段です。
例えば、Contax Planar 55mmF1.2なんて言うのは、
状態がよければ恐ろしく高いレンズです。
大抵は殆ど使用していないのではないかと思えるので、
殆どの中古商品が高いことになります。
これに比べて、Ricoh XR Rikenon 55mmF1.2は
随分と安いレンズです。
確か、中古なら1万円台後半で売っていたのではないでしょうか。

Ricoh XR Solar + XR Rikenon 55mmF1.2
冬のパリです。
なぜか、海外に行くときは安いセットになります。
でも、海外の方が人を意識せずにシャッターを切れます。
Yashica TL Electro X
午後になって温かくなってくると、
少し雪掻きをします。
この時期になると、
あれだけ降って手こずらせた雪も諦め気味で、
簡単に除雪ができます。
嬉しいですね。
今日は、ヤシカのM42マウント機のことを書いてみます。
それも、Yashica TL Electro X という機種です。
この機種の良いところは、
レンズを無限遠の位置にしても、ミラーが干渉しないので、
東独製の古いM42マウントのレンズが使用できます。
また、ヤシカのレンズも使用できます。
まあ、当然ですけど。

少し不思議なデザインです。
今のところ、動いていますが、
電子シャッター機で、いつ故障するか分かりません。
もっとも、カメラの部品の中には、
使用しないと駄目になり易いパーツもあるそうです。
少し雪掻きをします。
この時期になると、
あれだけ降って手こずらせた雪も諦め気味で、
簡単に除雪ができます。
嬉しいですね。
今日は、ヤシカのM42マウント機のことを書いてみます。
それも、Yashica TL Electro X という機種です。
この機種の良いところは、
レンズを無限遠の位置にしても、ミラーが干渉しないので、
東独製の古いM42マウントのレンズが使用できます。
また、ヤシカのレンズも使用できます。
まあ、当然ですけど。
少し不思議なデザインです。
今のところ、動いていますが、
電子シャッター機で、いつ故障するか分かりません。
もっとも、カメラの部品の中には、
使用しないと駄目になり易いパーツもあるそうです。
MinoltaAF50mmF1.4(2)
少し休んだらずっと休んでしまいました。
ブログ再開いたします。
暫く休んでいる間に、
中古の銀塩カメラ市場はいっそう冷え込んでしまった様です。
今は季節的にもダウンしている時期なのですが、
それにしてもAFカメラはさっぱりでそうです。
よほど珍しいものか、新品同様に綺麗なものでなければ、
殆ど売れません、とカメラ屋が言っていました。
若い人が参入してくれないと、こうした市場は拡大しませんし、
第一にメーカーが生産を止めてしまいましたからね。
修理屋さんも、修理依頼件数が昨年に比べてはっきり減少している、
とこぼしていました。
ただトイカメラが少し人気の様です。
さて、この人気どうなるのでしょうか。
ちなみにカメラの雑誌も、クラシックカメラ専科が休止となりました。
銀塩系では写真工業くらいでしょうか、まだ残ってるのは。
頑張って欲しいです。

この写真を撮影してから、ブログをサボっていたので、
季節が反転しています。
市内の古い木造アパートです。
別棟の話ですが、こうしたアパートに住むことに憧れた若い人がいて、
お風呂なんかを改造して、結構自分なりの生活を楽しんでいるようです。
ブログ再開いたします。
暫く休んでいる間に、
中古の銀塩カメラ市場はいっそう冷え込んでしまった様です。
今は季節的にもダウンしている時期なのですが、
それにしてもAFカメラはさっぱりでそうです。
よほど珍しいものか、新品同様に綺麗なものでなければ、
殆ど売れません、とカメラ屋が言っていました。
若い人が参入してくれないと、こうした市場は拡大しませんし、
第一にメーカーが生産を止めてしまいましたからね。
修理屋さんも、修理依頼件数が昨年に比べてはっきり減少している、
とこぼしていました。
ただトイカメラが少し人気の様です。
さて、この人気どうなるのでしょうか。
ちなみにカメラの雑誌も、クラシックカメラ専科が休止となりました。
銀塩系では写真工業くらいでしょうか、まだ残ってるのは。
頑張って欲しいです。

この写真を撮影してから、ブログをサボっていたので、
季節が反転しています。
市内の古い木造アパートです。
別棟の話ですが、こうしたアパートに住むことに憧れた若い人がいて、
お風呂なんかを改造して、結構自分なりの生活を楽しんでいるようです。
Minolta AF50mmF1.4
久しぶりにAF機を使用したら、
しかも小ぶりなミノルタα-Sweet Ⅱだったので、
とても軽くて便利でした。
古いMF機を使った後は、
最近の銀塩カメラの持つ機能の恩恵を感じます。
まあ、最近といっても既に数年前のことなのですが。
ミノルタαマウントの交換レンズは、
先回使用したAF24-50mmF4Nのほかに、
AF100mmF2と
今回取り上げるAF50mmF1.4しか持っていません。
ミノルタには有名なGシリーズのレンズもありますが、
今でも結構高くて手が出ません。
それに、きっとプロのような人が使われるのでしょう。
小ぶりなα-Sweet Ⅱには、
小ぶりなズームレンズか、そう明るくない単焦点レンズが似合います。
今回のAF50mmF1.4Nもよく似合っていると思います。
ただ、このレンズの収納式のフードは少し寸足らずのようです。
それでは明日、撮影に行ってきます
さて、明日から連休です。
よい週末をお迎え下さい。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF50mmF1.4
ミノルタのαマウント用のレンズはたくさん持っていないので、
分かりませんが、どうもNewタイプではないようです。
このレンズ、ボデイを買ったときに、
距離表示部のプラスティックカバーに疵があるからということで、
オマケについてきたものです。
こういうレンズって、割と好きですね。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet Ⅱを使用しAF50mmF1.4で撮影した結果です。
しかも小ぶりなミノルタα-Sweet Ⅱだったので、
とても軽くて便利でした。
古いMF機を使った後は、
最近の銀塩カメラの持つ機能の恩恵を感じます。
まあ、最近といっても既に数年前のことなのですが。
ミノルタαマウントの交換レンズは、
先回使用したAF24-50mmF4Nのほかに、
AF100mmF2と
今回取り上げるAF50mmF1.4しか持っていません。
ミノルタには有名なGシリーズのレンズもありますが、
今でも結構高くて手が出ません。
それに、きっとプロのような人が使われるのでしょう。
小ぶりなα-Sweet Ⅱには、
小ぶりなズームレンズか、そう明るくない単焦点レンズが似合います。
今回のAF50mmF1.4Nもよく似合っていると思います。
ただ、このレンズの収納式のフードは少し寸足らずのようです。
それでは明日、撮影に行ってきます
さて、明日から連休です。
よい週末をお迎え下さい。
Minolta α-Sweet Ⅱ + AF50mmF1.4
ミノルタのαマウント用のレンズはたくさん持っていないので、
分かりませんが、どうもNewタイプではないようです。
このレンズ、ボデイを買ったときに、
距離表示部のプラスティックカバーに疵があるからということで、
オマケについてきたものです。
こういうレンズって、割と好きですね。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet Ⅱを使用しAF50mmF1.4で撮影した結果です。
Minolta α-Sweet Ⅱ
近頃は、ここもすっかり涼しくなってきました。
朝晩は寒いくらいです。
皆さんのお住まいでは、どうでしょうか。
Minolta α-Sweet Ⅱに、
いまでは少し古いといわれる広角系ズームAF24-50mmF4Nが、
今回の散歩のお供です。
AFは撮影が楽でいいですね。
レンズの先端が素早くくるくる回って面白かった。
でも、特殊なフィルターを使う場合には、
少し問題でしょうけど。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
飛騨高山のがらくた市。
今年から毎月第一日曜日に開催されることになりました。ただし、寒い時期(晩秋から早春)は開催されません。出店は十数件で、この町の規模にあっています。写真は準備完了といったところ。一二時間小雨模様でしたが、歩き回るにはこのくらいが涼しくてよいかもしれません。出店者は皆さんプロです。しかし、茶器をはじめとする、器物がさっぱりで苦しいとのことでした。それでも、まあまあ人気があったのは、大正から昭和初期のガラスの生活骨董。小さな町ですからあまり掘り出し物はありませんが、町の一寸した催しとなっています。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
山野草の販売所。
以前は、みたらし団子を売っていたところです。値段は一鉢500円から。年配の方で好きな人が多いようです。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet Ⅱを使用し、AF50mmF1.4を付けてみます。
朝晩は寒いくらいです。
皆さんのお住まいでは、どうでしょうか。
Minolta α-Sweet Ⅱに、
いまでは少し古いといわれる広角系ズームAF24-50mmF4Nが、
今回の散歩のお供です。
AFは撮影が楽でいいですね。
レンズの先端が素早くくるくる回って面白かった。
でも、特殊なフィルターを使う場合には、
少し問題でしょうけど。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
飛騨高山のがらくた市。
今年から毎月第一日曜日に開催されることになりました。ただし、寒い時期(晩秋から早春)は開催されません。出店は十数件で、この町の規模にあっています。写真は準備完了といったところ。一二時間小雨模様でしたが、歩き回るにはこのくらいが涼しくてよいかもしれません。出店者は皆さんプロです。しかし、茶器をはじめとする、器物がさっぱりで苦しいとのことでした。それでも、まあまあ人気があったのは、大正から昭和初期のガラスの生活骨董。小さな町ですからあまり掘り出し物はありませんが、町の一寸した催しとなっています。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
山野草の販売所。
以前は、みたらし団子を売っていたところです。値段は一鉢500円から。年配の方で好きな人が多いようです。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet Ⅱを使用し、AF50mmF1.4を付けてみます。
Minolta α-Sweet Ⅱ
「イチオシの銀塩カメラ」は、
ミノルタのAF機、α-Sweet Ⅱを見ていきます。
このカメラはミノルタがコニカに買収される頃のもので、
新品でもすごく安く売っていました。
入門機であっても、最近のカメラは機能がたくさんあって、
いくらなんでもこんなに安くていいのかと思っていました。
結局は買わなかったけど、少し気になってはいました。
長野県のお店に立ち寄ったとき、
28mmからの標準ズーム付で、10000円を切っていました。
安いカメラが好きで、早速購入しました。
AF機は使用説明書がないと分かり難いので、
コニカミノルタのサポートサイトから、
ダウンロードしました。
サイトはここです。
http://ca.konicaminolta.jp/support/manual/
コニカミノルタは親切ですね。
で、暇なので、よくよんで見ようと思って、
印刷してみたら結構な量でした。
お散歩カメラとしては、
軽くって高性能です。
比較的小さな短焦点のレンズが似合いそうです。
今回はAF 24-50mmF4Nという市内のカメラで見つけたレンズを装着してみました。
売れ残りで、2万円。
少し高かったけど、新品はいいですね。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
もう少しストラップを綺麗にたたんでおけば良かった。
さて、このカメラは本当に小ぶりなカメラで、
実勢中古価格は5000~10000円。
いくらマレーシア製でもこの機能、
少し安すぎるような気がします。
輸出用はMinolta α-5ですが、α-Sweet Ⅱよりも、
少し機能が簡略化されていたような気がします。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet ⅡとAF 24-50mmF4の予定です。
ミノルタのAF機、α-Sweet Ⅱを見ていきます。
このカメラはミノルタがコニカに買収される頃のもので、
新品でもすごく安く売っていました。
入門機であっても、最近のカメラは機能がたくさんあって、
いくらなんでもこんなに安くていいのかと思っていました。
結局は買わなかったけど、少し気になってはいました。
長野県のお店に立ち寄ったとき、
28mmからの標準ズーム付で、10000円を切っていました。
安いカメラが好きで、早速購入しました。
AF機は使用説明書がないと分かり難いので、
コニカミノルタのサポートサイトから、
ダウンロードしました。
サイトはここです。
http://ca.konicaminolta.jp/support/manual/
コニカミノルタは親切ですね。
で、暇なので、よくよんで見ようと思って、
印刷してみたら結構な量でした。
お散歩カメラとしては、
軽くって高性能です。
比較的小さな短焦点のレンズが似合いそうです。
今回はAF 24-50mmF4Nという市内のカメラで見つけたレンズを装着してみました。
売れ残りで、2万円。
少し高かったけど、新品はいいですね。

Minolta α-Sweet Ⅱ + AF 24-50mmF4N
もう少しストラップを綺麗にたたんでおけば良かった。
さて、このカメラは本当に小ぶりなカメラで、
実勢中古価格は5000~10000円。
いくらマレーシア製でもこの機能、
少し安すぎるような気がします。
輸出用はMinolta α-5ですが、α-Sweet Ⅱよりも、
少し機能が簡略化されていたような気がします。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、引き続きMinolta α-Sweet ⅡとAF 24-50mmF4の予定です。
Minolta Paradjuster
「イチオシの銀塩カメラ」は、少しお休みをしていました。
休息日を書くと、そのまま止まってしまうのが、悪い癖です。
さて、今回はアクセサリーを取り上げました。
ヤフオクなんかを見ていますと、
例えば、ニコンのSマウントレンズのフードなど、
アクセサリーには比較的高い落札価格が付けられています。
しかもカメラやレンズは、メンテナンスが必要ですけど、
アクセサリーは通常メンテナンスフリーです。
儲けるならばアクセサリーでしょうか?
横道に逸れました。
取り上げたのはミノルタの二眼レフ用のパラジャスターです。
二眼レフは最近、若い人に人気だそうです。
左右が掴みにくく、ボクは苦手なのですが、
独特のスタイルは見ていて飽きません。
で、パラジャスターは、二眼レフのパララックスの補正に使用されました。
ジャッキのような簡単な構造ですが、ボデイにとりつけ、
そのボデイを上に持ち上げると、一定の高さで止まります。
元に戻すときには、レリースレバーを押すだけです。
でも、ボデイを持ちながらやらないと、
バタンと一度におちます。
注意してください(ボクは一度やってしまいました)。
これは、
専用の接写用外付けレンズと一緒になっていることが多いものです。
パラジャスターを手に取りながら、
「昔は苦労して写真を撮ったよ」
とカメラ屋のオヤジさん。
こんな昔話を聞けるのも、カメラ屋に通う楽しみかもしれません。


パラジャスター(上)と外付けレンズとともにパラジャスターを付されたMinolta Autocord初期型(下)
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Minolta α-Sweet ⅡとAF 24-50mmF4の予定です。
休息日を書くと、そのまま止まってしまうのが、悪い癖です。
さて、今回はアクセサリーを取り上げました。
ヤフオクなんかを見ていますと、
例えば、ニコンのSマウントレンズのフードなど、
アクセサリーには比較的高い落札価格が付けられています。
しかもカメラやレンズは、メンテナンスが必要ですけど、
アクセサリーは通常メンテナンスフリーです。
儲けるならばアクセサリーでしょうか?
横道に逸れました。
取り上げたのはミノルタの二眼レフ用のパラジャスターです。
二眼レフは最近、若い人に人気だそうです。
左右が掴みにくく、ボクは苦手なのですが、
独特のスタイルは見ていて飽きません。
で、パラジャスターは、二眼レフのパララックスの補正に使用されました。
ジャッキのような簡単な構造ですが、ボデイにとりつけ、
そのボデイを上に持ち上げると、一定の高さで止まります。
元に戻すときには、レリースレバーを押すだけです。
でも、ボデイを持ちながらやらないと、
バタンと一度におちます。
注意してください(ボクは一度やってしまいました)。
これは、
専用の接写用外付けレンズと一緒になっていることが多いものです。
パラジャスターを手に取りながら、
「昔は苦労して写真を撮ったよ」
とカメラ屋のオヤジさん。
こんな昔話を聞けるのも、カメラ屋に通う楽しみかもしれません。


パラジャスター(上)と外付けレンズとともにパラジャスターを付されたMinolta Autocord初期型(下)
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Minolta α-Sweet ⅡとAF 24-50mmF4の予定です。
イチオシの銀塩カメラ休息日(3)
台風が過ぎて、天気が落ち着いてきました。
皆さんのところはどうですか。
さて、今日は休息日です。少し休みます。


地下道(上)と町並み(下) Fuji Tiara Ⅱ
香港での撮影です。
特に香港らしさが現れているわけでは有りませんが。
フジのコンパクトカメラで、
28mmが搭載されているものは写りが良いという印象があります。
安っぽいカメラの代表であるFuji Cardia Travel miniは、
二焦点レンズを搭載していましたが、
その28mmの方は好きでした。
PS このブログでは縦写真が少し多い気がします。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、未定です。
皆さんのところはどうですか。
さて、今日は休息日です。少し休みます。


地下道(上)と町並み(下) Fuji Tiara Ⅱ
香港での撮影です。
特に香港らしさが現れているわけでは有りませんが。
フジのコンパクトカメラで、
28mmが搭載されているものは写りが良いという印象があります。
安っぽいカメラの代表であるFuji Cardia Travel miniは、
二焦点レンズを搭載していましたが、
その28mmの方は好きでした。
PS このブログでは縦写真が少し多い気がします。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、未定です。
Olympus μ-Ⅱ(2)
こんにちは
今日の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympusμ-Ⅱです。

コンパクトカメラの場合には、
ボデイとレンズを分けなくてよいので、
ブログを書く立場とすれば少し楽です。
このカメラは、本当にいいスタイルをしていますね。


橋(上)とゴミ箱(下) Olympus μ-Ⅱ
撮影は暑い頃でしたが、とても楽でした。
単焦点のコンパクトカメラは、
その搭載レンズの性能がよいことから人気があります。
ただ、あまり焦点距離の長いものはなく、
今では、ライカのコンパクトカメラについている40mmが一番長いものでしようか。
もう少しだけ長いものもあれば嬉しいけれど、
今では短くなることはあっても、
長いものはもう出ないでしょうね。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、未定です。
今日の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympusμ-Ⅱです。

コンパクトカメラの場合には、
ボデイとレンズを分けなくてよいので、
ブログを書く立場とすれば少し楽です。
このカメラは、本当にいいスタイルをしていますね。


橋(上)とゴミ箱(下) Olympus μ-Ⅱ
撮影は暑い頃でしたが、とても楽でした。
単焦点のコンパクトカメラは、
その搭載レンズの性能がよいことから人気があります。
ただ、あまり焦点距離の長いものはなく、
今では、ライカのコンパクトカメラについている40mmが一番長いものでしようか。
もう少しだけ長いものもあれば嬉しいけれど、
今では短くなることはあっても、
長いものはもう出ないでしょうね。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、未定です。
Olympus μ-Ⅱ(1)
こんにちは

オリンパスのカメラは、どれも小ぶりで、
高性能といったイメージがあります。
今回ご紹介するコンパクトカメラのμ-Ⅱは、
Minolta TC-1ほどではありませんが、
価格の割には35mmF2.8という最近では明るいレンズを搭載し、
スタイルの非常に良いカメラでした。
持ち運びに便利で、よく言われるように石鹸箱のようですが、
なかなか極めている、という感じがします。

過去形でご紹介しましたが、
中国や香港には、まだ新品が売ってあって、
というか売れ残っていて、大抵は一万円以内で購入できます。
ただ、ボデイ本体とリモコンと電池を別売する傾向にあって、
これは主にユダヤ系の人が経営していたNYのお店の販売方針と大差有りません。
今回ご紹介するのは、限定販売されたもので、特別色が施されています。
コレクターは限定品が好きな人が多いらしく、
市場ではこんなコンパクトカメラでも、
あまり見かけません。


Olympus μ-Ⅱ Ltd.
頃合のサイズのこのカメラは、小旅行にピッタシです。
先回、香港に行ったときには、
このカメラとフジのTiara Ⅱの二台を持っていきました。
本当に軽くて楽でした。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympus μ-Ⅱの撮影結果です。

オリンパスのカメラは、どれも小ぶりで、
高性能といったイメージがあります。
今回ご紹介するコンパクトカメラのμ-Ⅱは、
Minolta TC-1ほどではありませんが、
価格の割には35mmF2.8という最近では明るいレンズを搭載し、
スタイルの非常に良いカメラでした。
持ち運びに便利で、よく言われるように石鹸箱のようですが、
なかなか極めている、という感じがします。

過去形でご紹介しましたが、
中国や香港には、まだ新品が売ってあって、
というか売れ残っていて、大抵は一万円以内で購入できます。
ただ、ボデイ本体とリモコンと電池を別売する傾向にあって、
これは主にユダヤ系の人が経営していたNYのお店の販売方針と大差有りません。
今回ご紹介するのは、限定販売されたもので、特別色が施されています。
コレクターは限定品が好きな人が多いらしく、
市場ではこんなコンパクトカメラでも、
あまり見かけません。


Olympus μ-Ⅱ Ltd.
頃合のサイズのこのカメラは、小旅行にピッタシです。
先回、香港に行ったときには、
このカメラとフジのTiara Ⅱの二台を持っていきました。
本当に軽くて楽でした。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympus μ-Ⅱの撮影結果です。
Petri C.C Auto 35mmF2.8(2)
こんにちは

朝晩はかなり涼しくなってきました。
最近よく使っているM42マウントレンズ用ボデイに、
Petri35mmF2.8をつけて、感度100のポジカラーを入れて撮影してみました。

道端 Pentax MZ-3 + Petri 35mmF2.8
犬の散歩道から。

隣町 Pentax MZ-3 + Petri 35mmF2.8

近くの牧場 Petri 35(50mmF1.8付)
ペトリのRF機やコンパクトカメラには、結構色々な製品がありました。形状もユニークでした。例えば、
Petri Half
Petri Racer
Petri Color 35 Custom
Petri Computer
などがすぐに思い出されます。ペトリは無くなってしまったけど、存続していれば、Petri Computer 2.0なんか出したかもしれません。
さて、Petri 35には、1958年からグリーン・オ・マチックという、採光式のムライトフレームを採用したカメラが登場しています。距離計と採光式ブライトフレームを覆う窓にグリーンガラスを使用していたため、そう呼ばれています。その後、色々なレンズ、具体的には焦点距離45~50mm、明るさはF2.8~1.8、が付けられ、販売されていました。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympus μ-Ⅱの予定です。

朝晩はかなり涼しくなってきました。
最近よく使っているM42マウントレンズ用ボデイに、
Petri35mmF2.8をつけて、感度100のポジカラーを入れて撮影してみました。

道端 Pentax MZ-3 + Petri 35mmF2.8
犬の散歩道から。

隣町 Pentax MZ-3 + Petri 35mmF2.8

近くの牧場 Petri 35(50mmF1.8付)
ペトリのRF機やコンパクトカメラには、結構色々な製品がありました。形状もユニークでした。例えば、
Petri Half
Petri Racer
Petri Color 35 Custom
Petri Computer
などがすぐに思い出されます。ペトリは無くなってしまったけど、存続していれば、Petri Computer 2.0なんか出したかもしれません。
さて、Petri 35には、1958年からグリーン・オ・マチックという、採光式のムライトフレームを採用したカメラが登場しています。距離計と採光式ブライトフレームを覆う窓にグリーンガラスを使用していたため、そう呼ばれています。その後、色々なレンズ、具体的には焦点距離45~50mm、明るさはF2.8~1.8、が付けられ、販売されていました。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Olympus μ-Ⅱの予定です。
Petri C.C Auto 35mmF2.8
こんにちは

今日の「イチオシの銀塩カメラ」は、
カメラではなくてレンズです。
ペトリ(栗林製作所)のM42マウントレンズ、
35mmF2.8をご紹介します。
今はなくなりましたが、この頃のブランド名、
ペトリ、ミランダ、カロ(コーワ)など、
なんとも不思議な響きがあります。

ペトリの一眼レフは、最初M42マウントでしたが、
次は、独特のスピゴットマウントを採用し、
最後は、再びM42マウントに戻りました。
なかでも、Contarexに似ているPetri 7が人気です。
この機種の対応レンズも、良く見ると安っぽいものの、
歴代ペトリレンズの中では少し華があります。
Contarexはセレン式の露出計ですが、
Petri 7はCdsを使用しています。
ペトリは安価路線で市場に向かっていったそうです。
一眼レフカメラはペンタ部が少し出た独特な形をしていましたが、
最後のMF-1になると落ち着いた形状のものになりました。
むしろ、勢いが無いというか、つまらないというか、
そういうボデイになりました。

M42マウントレンズは、あまり種類が無かったのではないでしょうか。
もっとコロコロした28mmF2.8のほか、市場によくある55mmF1.8、
それと最後のほうに出たパンケーキレンズ45mmF2.8など数本くらいでしょうか。
次回は、Pentax MZ-3と組み合わせでの撮影結果です。


Petri C.C Auto 35mmF2.8 for M42 mnt.
赤い紙を敷いて撮影しました。
独特のブリーチマウントのボデイは、部品が脆く、案外修理がし難いとのことで、M42マウントのレンズを集めました。もっとも、ほかには55mmF1.8しか持っていませんが。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Petri 35mmF2.8 for M42 mnt.で撮影した結果です。

今日の「イチオシの銀塩カメラ」は、
カメラではなくてレンズです。
ペトリ(栗林製作所)のM42マウントレンズ、
35mmF2.8をご紹介します。
今はなくなりましたが、この頃のブランド名、
ペトリ、ミランダ、カロ(コーワ)など、
なんとも不思議な響きがあります。

ペトリの一眼レフは、最初M42マウントでしたが、
次は、独特のスピゴットマウントを採用し、
最後は、再びM42マウントに戻りました。
なかでも、Contarexに似ているPetri 7が人気です。
この機種の対応レンズも、良く見ると安っぽいものの、
歴代ペトリレンズの中では少し華があります。
Contarexはセレン式の露出計ですが、
Petri 7はCdsを使用しています。
ペトリは安価路線で市場に向かっていったそうです。
一眼レフカメラはペンタ部が少し出た独特な形をしていましたが、
最後のMF-1になると落ち着いた形状のものになりました。
むしろ、勢いが無いというか、つまらないというか、
そういうボデイになりました。

M42マウントレンズは、あまり種類が無かったのではないでしょうか。
もっとコロコロした28mmF2.8のほか、市場によくある55mmF1.8、
それと最後のほうに出たパンケーキレンズ45mmF2.8など数本くらいでしょうか。
次回は、Pentax MZ-3と組み合わせでの撮影結果です。
Petri C.C Auto 35mmF2.8 for M42 mnt.
赤い紙を敷いて撮影しました。
独特のブリーチマウントのボデイは、部品が脆く、案外修理がし難いとのことで、M42マウントのレンズを集めました。もっとも、ほかには55mmF1.8しか持っていませんが。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Petri 35mmF2.8 for M42 mnt.で撮影した結果です。
Canon P
こんにちは

今日の「イチオシの銀塩カメラ」はCanon Pです。
これはキヤノンのレンジファインダー機(RF機)の中でも、
ファインダーなどが簡略された大衆機という位置づけです。
黒モデル以外は中古市場で結構安く入手できます。
キヤノンのRF機では、とりわけ、Canon ⅣSb改、Canon ⅥLが人気ですが、
個人的には結構、このCanon Pが好きです。
フレームは、35/50/100mmの枠が出たままなのですが、
全体的にスッキリしたデザイン、
これが好きなのかもしれません。

シャッター膜が金属製で、使用していると、
次第に「皺」がよってきます。
これが、まあ唯一の欠点ですが、人間に似ています。
先回、Voightlaender Bessa Rを使用したためか、
やっぱり金属製はいいな、と感じました。

当時、LマウントのRF機、
いわゆるライカコピー機がいろいろ出されましたが、
日本ではCanonのRF機が一番の様に思います。
中古市場に多く出回っているので、
あまりそれを感じませんが。


Canon P + Elmar 50mmF3.5
このElmarはノンコートと言われて買いました。
ちゃんと、フードを付けなさいということでしょうか。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Petri 35mmF2.8 for M42 mnt.です。

今日の「イチオシの銀塩カメラ」はCanon Pです。
これはキヤノンのレンジファインダー機(RF機)の中でも、
ファインダーなどが簡略された大衆機という位置づけです。
黒モデル以外は中古市場で結構安く入手できます。
キヤノンのRF機では、とりわけ、Canon ⅣSb改、Canon ⅥLが人気ですが、
個人的には結構、このCanon Pが好きです。
フレームは、35/50/100mmの枠が出たままなのですが、
全体的にスッキリしたデザイン、
これが好きなのかもしれません。

シャッター膜が金属製で、使用していると、
次第に「皺」がよってきます。
これが、まあ唯一の欠点ですが、人間に似ています。
先回、Voightlaender Bessa Rを使用したためか、
やっぱり金属製はいいな、と感じました。

当時、LマウントのRF機、
いわゆるライカコピー機がいろいろ出されましたが、
日本ではCanonのRF機が一番の様に思います。
中古市場に多く出回っているので、
あまりそれを感じませんが。


Canon P + Elmar 50mmF3.5
このElmarはノンコートと言われて買いました。
ちゃんと、フードを付けなさいということでしょうか。
次回の「イチオシの銀塩カメラ」は、Petri 35mmF2.8 for M42 mnt.です。















